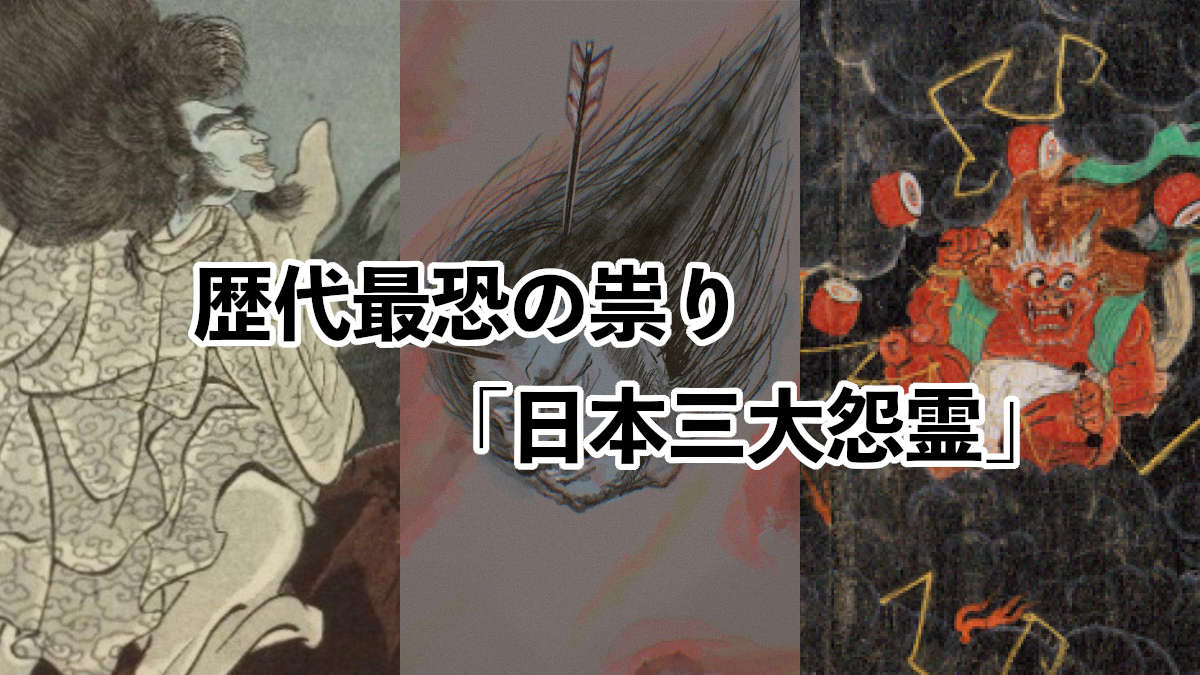
建国2600年ともいわれる日本の歴史。その歴史の中には力ある立場の者が、不幸の中で壮絶な最後を迎えた者も存在する。そんな人物は強い怨念を残しこの世を去っている。その強大で強い未練の念が大怨霊となって世を生きる人々に災いを降りかざす。
今回は日本の歴史上でも最強で最恐とも言われる「日本三大怨霊」について、その人物の壮絶な人生や、実際にあったと言われる祟りの事例、近代にまで続いている祟りを一挙ご紹介。
そもそも祟りと呪いの違い
呪いとは、人為的な怨念によって相手に恐怖や不幸を与えるもの。一方祟りとは神仏や霊魂などによる超自然的な存在によるもので、俗にいう「天罰」に近い意味合いがある。呪いの源は生きた者による現在進行形の怨念なのに対し、祟りの原因はすでに亡くなっている者からの怨念が多い。
これから紹介する三大怨霊と言われる方々は、その壮絶な人生に幕を降ろした後、生前に関係のあった人に災いが降りかかった事から長年恐れられていった存在でもある。
1.平将門の祟り

平安時代の豪族である「平将門」。彼は朝廷からの独立を目指して自らを「新皇(しんすめらぎ)」と称し、「平将門の乱」という戦を起こした人物で有名である。天下を支配する者を意味する皇を名乗れば当然、当時の日本を支配するもの朝廷からは朝敵認定された。そして朝敵の討伐を職務とする征夷大将軍に任命された藤原忠文らによって討たれてその生涯を閉じた。
その後、平将門の首は平安京へ運ばれ晒し首となる。
これは日本史において、現在確認がとれる「晒し首」の最初の事例となり、伝承ではこの後に様々な出来事が起こる事となってしまう。
平将門の祟りの始まり

晒し首にされた平将門だが数ヶ月もの間、その首は腐る事もなく目をカッと開き歯を食いしばった形相をしていたという。
ある歌人がその様子を歌にしたところ、首は突然笑い声を上げ「今ひとたび戦を」と言い残し、雷鳴が轟くなか東の方角へ飛び去っていった。そして途中で力つき落下した場所が、東京大手町にある首塚「将門塚」だと言われている。
近代においての平将門の祟り

天慶3年(西暦940年)から1000年以上経過した1923年にも、この将門塚に関わった者達に祟りが襲いかかる事態となっている。
関東大震災後、都市の再開発のため首塚の場所に大蔵省の仮庁舎が建てられるも、その後工事関係者だけでなく大蔵省の職員や大臣までも14名が相次いで亡くなってしまう。その後、仮庁舎はすぐに取り壊された。
昭和15年、平将門没ちょうど1000年で大蔵庁舎が落雷により全焼、大蔵省主導の祭祀が行われ慰霊につとめる。
太平洋戦争後、GHQにより首塚を駐車場にしようとした際に、工事に携わっていた日本人が事故で亡くなる。
大都市東京の大手町のど真ん中に存在する首塚だが、その利便性の高い立地により今まで何回か土地の利用計画が進められてきた。
だが祟りが原因なのか不可解な出来事が相次いだ事で、いくつもの利用計画は中断または白紙となり、現代においても不可侵の場所として崇められる事となった。
2.菅原道真の祟り

今では学問の神様として有名で親しまれる存在だが、かつては日本史上最強で最恐の怨霊として畏怖されていた。
そんな彼の人生は、幼少期より頭が良く神童として有名で、その明晰さからも宇多天皇からの信任も厚く朝廷の要職を歴任、家格を無視するほどに異例のスピードで出世を果たしていった。まさに神童の名に相応しい出世街道といえる。
しかし、その前例なき異例の出世から朝廷内の他の貴族からの嫉妬や反発も強く、この事が華々しい彼の人生に大きな影を落とす事になってしまう。
朝廷内でどこからともなくある噂が目立つ様になる。それは道真が当時の天皇を廃し、自分の女婿を天皇の地位に付けようとしている噂だった。これはあくまでも噂であったが、当時の醍醐天皇は重く受け止め、道真とその一族を日本の果て「九州の太宰府」へと左遷してしまう。
人の嫉妬により、彼は言われなき罪で出世街道を断たれてしまったのだ。
当時、天皇を譲り上皇となり菅原道真と親交厚かった宇多上皇は、何とか道真を助けようとするも叶う事はなかった。
道真は今までの生活ではありえない食うのもやっとな生活を続け、自身の潔白が証明されると信じながらも絶望の中その生涯を閉じてしまう。
当時に起こった菅原道真の祟り

道真が亡くなった5年後、左遷のきっかけとなった人物、藤原菅根が亡くなる。
その翌年、菅原道真の宿敵でもあった藤原時平が39歳の若さで突如として命を落とす。
数年後、菅原道真左遷の首謀者源光が狩りの途中に沼で溺れて命を落とす。
さらに左遷を決定した醍醐天皇の皇子やその息子である孫までもが次々と病気で亡くなる。
この様に、菅原道真の失脚と左遷に関わった人物たちが亡くなっていったが、祟りであると畏怖される決定的な出来事として、延喜8年に起こった清涼殿落雷事件がある。
当時干ばつが見舞われた都で、道真を左遷した醍醐天皇のいる清涼殿で雨乞いの朝議が行われている最中に落雷が直撃し火事が発生、その出来事で多くの人が亡くなってしまう。その亡くなった人たちの中に、道真を疑い監視を命じた藤原清貫がいた事から道真の祟りの噂は一気に広まる事態となった。雷により政敵が命を落とした事で道真を雷神とみなし恐れられる様になる。
後に、この出来事にショックを受けた道真を左遷した醍醐天皇は体調を崩し、3ヶ月後に失意の中生涯に幕を閉じている。
近代でも残る菅原道真の祟りの影響
清涼殿落雷事件、この事に恐怖を感じた朝廷は道真が生涯を閉じた地「太宰府」に太宰府天満宮が建てられ鎮魂を祈る事となる。
長い年月が過ぎ道真の祟りが風化した現代では、道真の明晰さだけが残り学問の神様として親しまれる事となっているのである。
実は、清涼殿落雷事件の恐怖は現代でもある言葉に込められ伝わっている。雷がなったときに唱える雷除けの呪文「くわばらくわばら」という言葉がある。
比較的有名で聞いた事もある人が多いこの言葉だが、この「くわばら」は雷神である藤原道真の領土であった桑原(くわばら)からきており、雷が鳴ったら「ここは桑原桑原、菅原道真の領土であるから雷を落とさないで」という意味で、当時から数百年経過した現代でも当時の人々が感じた畏怖が伝わっている。
3.崇徳天皇の祟り

平安時代後期に生まれ第75代天皇として即位した人物であり、歴代の天皇の中で名前に「徳」が付く数少ない人でもある。
崇徳天皇は鳥羽天皇の第一皇子として生まれ、父親の譲位により僅か5歳という年齢で第75代目の天皇の地位に着く事となった。そんな彼だが、ある理由により父親から疎まれていた。その理由とは、実の父親が違うのではないかという疑惑だ。
5歳という年齢で政ができるはずも無い彼は、実権は父親に握られたままのお飾りとして存在し、父親に別の子供ができると崇徳天皇はその地位を譲る様に迫られてしまう。天皇の地位を譲り上皇となった後でも、前上皇である父親に実権を握られたまま冷遇された人生を送る事となる。
そして第76代の近衛天皇が亡くなり、崇徳上皇(元天皇)の子が天皇になるチャンスが到来した際にも、本来直系になる崇徳上皇の子が天皇になれず別の者がその地位についてしまう。さらに鳥羽上皇(父親)が亡くなるも、彼の遺言である「自分の遺体を崇徳に見せるな」という言葉により、彼は父親との最後の面会も許される事はなかった。
その後、崇徳上皇は左大臣と手を組んでクーデターを起こすのではと噂されるようになる。クーデターについて身に覚えのない崇徳上皇は、身の危険を感じ側近とともに邸宅を脱出し避難しようとするも、翌日には左大臣が実際に軍を上げてしまい、噂は真実となってしまった。
そして「保元の乱」が勃発、敗走した崇徳上皇は頭を丸めて出家の意志を示すも許されず、島流しの刑となり二度と京に帰る事なく生涯を終えてしまう。
崇徳上皇は島流し後に、保元の乱で亡くなった人を供養するため写経を京に送るも突き返されてしまう。さすがに崇徳上皇はこれに激怒。自分の舌を噛み切り滴る血で突き返された写経に「日本国の大魔縁となり、皇をとって民とし、民を皇となさん」と書き示した。
この後、彼は生涯に渡り髪や爪を切る事もせず、その姿はまるで夜叉であったという。
親の愛を受けず、そして周囲の人間から疎まれ時には利用される。そんな人生を送った彼の無念は怨念となり…。
当時に起こった崇徳天皇の祟り

安元2年、崇徳上皇の敵対派閥である後醍醐派の側近が相次いで命を落とす。
その翌年の安元3年、「安元の大火」「延暦寺の強訴」「鹿ヶ谷の陰謀」と災害や社会情勢の不安定化につながる出来事が立て続けに起こり、動乱の時代の幕が開ける。
この様な出来事に危機を覚えた当時の朝廷は、第75代目の彼に儒教において最高位の「徳」の字をつけた「崇徳」の名を付け、保元の乱の戦場跡に崇徳院廟を建てる事で鎮魂・慰霊につとめた。
近代でも残る崇徳天皇の影響
生まれながらに疎まれ続ける生涯を送った崇徳天皇だが、彼が亡くなった数百年後にもその生涯と怨みの影響は色濃く残る事となる。
主な影響として
後醍醐天皇に曽孫が崇徳天皇の御陵の近くを通った際に慰霊を行うと、夢に彼が現れて京に残した家族の守護を願う。その影響で崇徳天皇の遺児が皇位につく。
数百年後の江戸時代後期の読み物「雨月物語」の怨霊のモチーフとなった。
明治天皇の即位の際には、崇徳天皇が亡くなった讃岐に勅使を送り彼の御霊を京都に帰還させる。
昭和天皇期、崇徳天皇八百年祭にあたる1964年には、崇徳天皇陵に勅使を遣わして式年祭を執り行った。
この様に昭和時代までの約800年にも渡り、後世を生きる人間の行動に影響と畏怖を与えている。
以上が数百年にも渡り、日本で恐れられてきた三大怨霊についての紹介です。雷が鳴った時のおまじない「くわばら、くわばら」の語源や、天皇家に「徳」の字が少ない理由など、雑学かねた最恐三大怨霊の紹介でした。